たたかれて育った人は「わが子をたたく」? 子育ての“悪い連鎖”を断ち切る3つの意識
親から受けた子育ての方法を、自分の子どもにも再現してしまう「連鎖」の傾向があるのではないか――。そう指摘する筆者が考える、“断ち切るための意識”とは。

「今の自分があるのは、親がたたいて厳しく育ててくれたからだ。だからわが子も甘やかさず、厳しくたたいて育てたい」。自身の経験から、そんなふうに言う人がいます。でも、もし過去にタイムスリップしたら、そこには納得できない自分の姿があるかもしれないと、子育て本著者・講演家である私は思います。
なぜ、つらい過去をよしとするのか。「自分の親からされた子育てを否定することは、自分の人生を否定すること」、だから無意識にそれをよしとし、体罰を肯定してしまうのかもしれません。
虐待などでトラウマを受けた子どもの心理臨床活動を行う西沢哲さんの著書「子ども虐待」(講談社現代新書)に、次の一文があります。
「自分自身が身体的虐待などの暴力を受けて育ったという親は、その経験から『子育てには体罰が必要』という、体罰を肯定的にとらえる養育観を持つことがある。こうした養育観を背景に、『言ってもきかないときには叩(たた)いてでも教えるのが親の務め』といった具合に体罰をともなう『しつけ』を日常化させやすい」
子どもは親を選べない
ある病院の待合室で聞こえてきた会話です。診察室から出てきた親が、子どもにこう語りかけていました。
「我慢して偉かったね。注射、痛かったね。怖かったね。おうちに帰っておやつ食べようね」
優しい声に、ジーンときてしまいました。というのも、私の母は対応が違ったからです。
母は、私が泣くと「そんなことくらいで泣くんじゃない!」「注射なんて痛いのは一瞬でしょ!」「泣き虫ね!」「いつまでも泣いてないの!」と怒りました。注射が痛くて泣いているのに、泣いていることを怒られるのです。
待合室で、私は「親によってこうも違うものか…気持ちに寄り添える親に育てられた子どもは本当に幸せだなあ。悲しいかな、子どもは親を選べないもんね」と思いました。母は「強い子に育ってほしい」という願いで、私に厳しいことを言っていたのだと思いますが、強い子になるどころか、オアシスを失った私は不安感が高まり、注射嫌いはますますひどくなりました。
読んだ子育て本や、ネットサーフィンで得た情報……。今、無意識にしている子育ての「手本」は何でしょうか。
「子どもは褒めて育てよ」「自己肯定感を育てよ」「承認欲求を満たせ」…耳にタコができるほど聞いて、もはや聞き飽きた言葉ではないでしょうか。しかし、これらを実行できないのは、自分自身が過去に親から褒められたことがなく、ダメ出しばかりされていたために、わが子にそれを再現するのが難しい――。そんな親もいるかもしれません。
「子育ての仕方に正解はないから」と思う人もいるでしょう。確かに、学校の保健体育で「妊娠のメカニズム」はしっかり習っても、子育ての仕方について教わることはありません。また、妊娠中にパパママ学級に通って、授乳や沐浴(もくよく)、オムツ交換については教えてもらえても、子育てをする上で絶対にやってはならないことを聞くチャンスはありません。
子育ての仕方の手本は「自分の親」となり、意識する・しないにかかわらず、自分自身が親から受けた子育てを、わが子にも再現しやすくなります。
![大人んさー [otona × answer]](https://otonanswer.jp/wp-content/themes/pc/common/img/logo.svg)




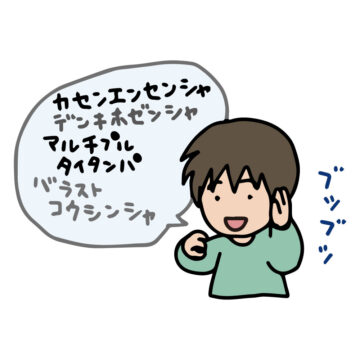




コメント