「生活苦しい」…長引く「物価高」が国民を殺す!? “栄養格差”拡大し、日本人の短命化が進みかねないワケ
物価高が将来的に国民の健康に与える影響について、評論家が解説します。

近年、原材料価格の高騰や円安などの影響で食料品や日用品などの価格が上がり続けており、家計のやりくりに苦労している人は多いのではないでしょうか。SNS上では「物価高で生活が苦しい」という声が多く上がっており、食費を節約するために1食当たりの食事量や1日当たりの食事の回数を減らす人もいます。
評論家の真鍋厚さんは、物価高が続くと国民の間で栄養格差や健康格差が大きく広がり、子どもの発育や国民の寿命に大きな影響を与える可能性があると指摘します。物価高が続いた場合に想定される将来的なリスクについて、真鍋さんが解説します。
米が高くパンやパスタを多めに食べる家庭も
物価高が止まりません。帝国データバンクによると、2025年9月の飲食料品値上げは、合計1422品目となりました。食品分野別では、たれ製品やソース、マヨネーズ、ドレッシング類を中心とした「調味料」(427品目)が最多で、「加工食品」(338品目)や「菓子」(291品目)のほか、「乳製品」(138品目)でも一斉値上げとなっています。
財布とにらめっこしながら、ディスカウントストアやスーパーのタイムセールなどを利用しても、空前の物価上昇の前では焼け石に水で、出費が増えている家庭が大半でしょう。外食をやめたり、割引商品だけを買ったり、材料が安い料理を大量に作ったりするなど、節約でストレスがたまっている人は多いと思います。
物価高の話は、家計負担の観点から話題になりがちですが、実は、中長期的にはもっと深刻な問題を引き起こす可能性があります。それは栄養面、健康面への影響です。一般的に、偏った食生活は、身体の形成や心理傾向、パフォーマンスに直結するものです。子どもなら学力や発育状況、高齢者なら持病や加齢により心身が老い衰えた状態である「フレイル」などに反映されることは容易に想像できます。
例えば、朝食を食べるか食べないかが、学力格差や体力格差につながることを示すデータがあります。文部科学省の調査では、朝食を毎日食べている小中学生と、まったく食べていない小中学生の間には、各教科の平均正答率の差が約15ポイントあることが分かりました(令和6(2024)年度「全国学力・学習状況調査」)。
また、スポーツ庁の調査では、毎日朝食を食べる子どもほど、体力合計点が高い傾向にあることが示されています(令和6(2024)年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」)。食事の回数が通常より少なかったり、栄養が偏っていたりすると、同様の影響が生じることは論をまたないと思われます。
しかも、経済格差は食生活に表れやすい傾向にあります。貧困ライン以下の世帯(低収入)の子どもと、貧困ラインより高い収入の世帯(低収入以外)の子どもを比較した調査では、「休日の朝食欠食:食べない・食べないこともある」(1.6倍)、「家での野菜摂取頻度:週3日以下」(2.0倍)、「インスタント麺・カップ麺の摂取頻度:週1回以上」(2.7倍)、「(同)月1~3回」(1.6倍)の項目で、前者が後者を上回りました(※1)。
そうすると何が起こるかは明らかです。物価高による欠食や栄養不足が続くことによって、子どもたちの心身に多大な悪影響が及ぶことが考えられるからです。先述のテストの点数の成績や体力だけではなく、朝食を抜く若年層は、朝食を習慣的に取っている人に比べて、うつの症状があると報告することが多いという研究結果もあるように、食生活はメンタルヘルス不調にも関連することも示されています(※2)。
つまり、物価上昇に伴う経済格差が大きくなることによって、適切な回数の食事や栄養がある食事を子どもに提供できなくなると、収入が低い世帯ほど子どもの成長が遅れたり、学業や運動能力に支障を来したりするとともに、心も不安定になる可能性が高くなる傾向にあると言えます。これは、想像以上に恐ろしいことです。
なぜなら、子どもだけの問題ではないからです。経済的に困難な状態にある子育て家庭を対象に、2025年7月にNPOが行った調査では、米が十分に食べられないときの工夫で「パンやうどん・パスタ(麺類)など、ほかの主食で代替する」が81.3%と最も多かった一方で、「保護者が食べる米の量を減らす」(73.9%)、「保護者の食事の回数を減らす」(54.1%)と、保護者が自分の食事を減らす選択を余儀なくされている現状が明らかとなりました(※3)。
この物価高で、私は現役世代から「これを機に1日2食にした」という話をよく聞くようになりました。まれに1日2食を1食にしたという人もいるぐらいです。
先述の調査結果ではありませんが、子どもにパンやパスタを多めに与えて満腹感を出しているといった話もたびたび耳にしますが、その場合は糖質に偏った食事になります。糖質を多く摂取すると、食後に血糖値が急上昇し、その後、急降下する状態である「血糖値スパイク」が生じ、イライラや不安感などを引き起こしやすくなるとされています。糖質を多めに摂取する食生活を続ければ、肥満や糖尿病などの生活習慣病にかかるリスクが高まります。
当然ですが、大人であっても食費の切り詰めによって偏食に陥れば、仕事のパフォーマンスに影響が出てしまいます。子どもとまったく同じ理由で、能力や気分が落ち込む可能性が高いからです。これでは家族を支えるための労働生産性が低下しかねず、仮にそのせいで収入が減少することになれば本末転倒でしょう。
それこそ物価高が長期化すれば、もっと恐ろしい事態を引き起こしかねません。高齢者の場合、持病やフレイルの悪化などによって、最悪死亡が早まるからです。まさに「栄養の切れ目」が「命の切れ目」になるのです。社会疫学研究の第一人者である医学者のイチロー・カワチは、近年、日本で「命の格差」が急激に広がっており、「長寿国家」が瓦解すると警鐘を鳴らしています(NHKスペシャル取材班『健康格差 あなたの寿命は社会が決める』講談社現代新書)。
すでに米国と英国では、過酷な「栄養格差社会」になっています。「健康的な食品は、健康的ではない食品に比べてカロリー当たりの値段が2倍以上高く、入手も困難である」「国民のうち最も恵まれない人々の5分の1は、政府が推奨する健康的な食事を取るためには可処分所得の45%を食費に費やす必要があり、子どもがいる世帯ではその割合は70%に上昇する」(※4)といった実態があり、低所得者層ほど病気になりやすく短命になりやすいという傾向が加速しています。
端的にいえば、「物価高は人を殺す」のです。しかも、じわりじわりと薄い毒を飲まされるようにして、人々の心身にダメージを蓄積させていきます。ですが、高齢者や中高年者の持病や突然死の原因、あるいは子どもの学習意欲の低下や感情の乱れについて、「物価高」が原因だと主張する人はほとんどいないでしょう。そのように主張しても「自己責任」で片付けられるのが関の山です。「自己管理ができていないのが悪い」というお決まりのフレーズです。
しかし「栄養格差社会」がもたらす負の連鎖は、結局はブーメランのように私たちの社会に大きな負担として返ってくるのです。それは、マクロ的には医療費の増大による社会保険料の上昇といった形かもしれませんし、ミクロ的には血糖値の乱高下で粗暴になった人から直接、何らかの被害を受けるという形かもしれません。
いずれにしても、「自己責任論」では何も解決できず、誰も得はしないことを肝に銘じるべきでしょう。
【参考文献】
(※1)社会経済的要因と健康・食生活/2014年10月6日/厚生労働省 社会・援護局 生活保護受給者の健康管理に関する研究会
(※2)Breakfast skipping and depressive symptoms in an epidemiological youth sample in Hong Kong: the mediating role of reduced attentional control/2025年5月22日/Frontiers in Psychiatry
(※3)経済的に困難な子育て世帯の子ども1.4 万人の食と生活の実態調査報告書-2025 年「子どもの食 応援ボックス」申込者7856世帯対象-/2025年7月/公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
(※4)『The Broken Plate 2025』/2025年1月29日/The Food Foundation
(評論家、著述家 真鍋厚)
![大人んさー [otona × answer]](https://otonanswer.jp/wp-content/themes/pc/common/img/logo.svg)















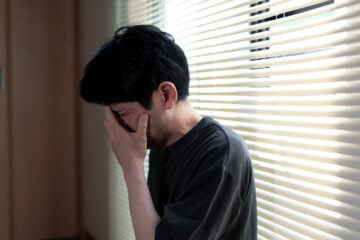


コメント